どのような釣りを行う場合でも、ターゲットに合わせた仕掛けを作るということが重要ですが、その第一歩は釣り糸選びから始まります。
これから海釣りを始める入門者さんや、あるいは釣りを始めたばかりの初心者さんは、始めから道糸(ライン)が巻かれたリールを入手し、使用するケースが多いと思います。
仕掛けにおいても、ハリス付きの釣り針を使用したり、更にサルカンやウキもセットになった完成仕掛けで、道糸に結ぶだけで釣りができる製品を購入したりと、手軽に釣りを楽しまれている方も多いでしょう。
もちろん、このような楽しみ方を否定することはありませんが、決まった規格の製品には自由度がなく、コストも割高だというデメリットがあります。
徐々に釣りの経験を重ねていくと、自分でリールの糸を巻き替えたり、状況に応じてバラ針を結び替えたりと、ある程度の仕掛けは自分で作るようになってきます。
今、本記事をご覧頂いている方の多くは、そのレベルまで到達された方であろうと思います。
ここでは、仕掛けを作る際に必ず必要となる知識で、釣り道具の中で最も重要性の高い釣り糸(ライン)の種類や特徴について紹介します。
釣り糸(ライン)の種類と素材の特徴
釣り糸の種類(ラインの種類)について紹介する場合、以下の2点について別々に考える必要があります。
釣り糸にまつわる2つの種類
- 釣り糸の用途の違いによる種類
- 釣り糸の素材の違いによる種類
まず一点目についてですが、釣り糸の用途は大きく分けると二つに分かれます。
簡単に一言で表現すると、『リールに巻いて遠くまで仕掛けを飛ばすために使う釣り糸』と、『仕掛けを作るために使う釣り糸』です。
用途が異なれば、求められる釣り糸の性能も変わってくるので、釣り糸選びはここからスタートします。
そして、もう一点は、釣り糸の素材に対する種類の違いですが、釣り糸の種類について調べる方のほとんどは、自分の釣り方に合った釣り糸の素材を調べているものだと思います。
現在、釣り糸は大きく分けると4種類の素材の釣り糸(ライン)と、これらを組み合わせた複合ラインが主流です。
ここでは、この2点について別々に紹介していきます。
釣り糸とは

釣り糸は用途と釣り方に応じて多種多様
釣り糸とは、言わずと知れた釣りに使う細い糸のことですが、極端な話をすると釣り糸と釣り針さえあれば釣りはできます。
釣りにとってはそれだけ重要な釣具ということになりますが、釣り糸の種類を紹介する前に、少しだけ寄り道をしたいと思います。
今ではお歳を召した方でないと知らないかも知れませんが、釣り糸はもともと【テグス】と呼ばれていました。
これは釣り糸というものが、もともとヤママユガの近縁種のテグスサンの絹糸腺から作った天蚕糸(てぐす)や、絹糸などの天然繊維が使用されていた事に由来します。
これらは結び繋ぐことで必要な長さにして使われていたわけですが、戦後まもなく、化学繊維のナイロンが釣り糸として採用され、繋ぎ目のない1本の糸(モノフィラメント)が登場したことで、釣りの歴史が大きく歩を進める転換点になりました。
今でもなおナイロンラインは釣り糸の主流として使われており、これがいかに釣りに適した素材であるかを物語っています。
その後、合成繊維が普及してからはナイロン以外にも、フロロカーボンやポリエチレン、ポリエステルなどが用途に応じて使われるようになり、これら合成繊維で作られた釣り糸は、釣り初心者の釣果をも飛躍的に伸ばす結果につながりました。
また、現在ではモノフィラメントだけでなく、極細の合成繊維の原糸を、複数本編み込んで1本にしたブレイデッドライン(撚り糸)も至極一般的に使用されるようになりました。
このあたりの釣り糸の素材に関する内容は、その特徴を中心に後ほどもう少し詳しく紹介したいと思います。
ちなみに、釣り糸は大きく分けると2種類に分かれ、一つは道糸(ライン)と呼ばれ、もう一つはハリス(仕掛け糸)と呼ばれます。
これは冒頭でお伝えした、釣り糸の用途の違いにあたりますが、まずは、この違いについて簡単に触れておきましょう。
道糸とは(ラインとは)
道糸(みちいと)とは、リールに巻いて使用する釣り糸で、仕掛けをより遠くへ飛ばすために使うことが主な目的の糸です。
ルアーフィッシングにおいては、道糸のことをラインと呼びますが、釣り糸全体をラインと表現することもあります。
また、リールを使わない延べ竿の仕掛けにおいては、釣り竿の先端(リリアン)からサルカン(スイベル)まで、あるいは次項で紹介するハリスの結束部分までに使う釣り糸のことを指します。
道糸とターゲットとなる魚の間には、ハリス(リーダー)を用いるのが一般的で、道糸は直接的に魚に関与しないので、太さによる影響は限定的です。
それゆえ、道糸はハリスに較べると、太くて強度が強いものを用いるのが一般的です。
ただし、後で記載しますが、一部の素材では細くても強度が高いものもあります。
道糸の選び方は、仕掛けの飛ばしやすさ(遠投性)、糸の見えやすさ(視認性)、沈みやすさ(沈降性)など、各々の釣り方に求められる性能に合わせて選びます。
ハリスとは(ショックリーダーとは)
前述の道糸に対して、ハリスとはサルカンや道糸との結束部から、釣り針までの間で用いられる釣り糸の呼称で、仕掛け糸とも呼ばれます。
また、ルアーフィッシングにおいてはハリスも呼び名が異なり、ショックリーダーとか単にリーダーと呼びます。
道糸とは違って、ハリスは釣り針やルアーと繋がる点で魚により近い位置にあることから、魚に警戒されない為に、なるべく細いものを用いる必要があります。
仕掛け糸の中には、胴突き仕掛けに使う幹糸(モトス)や枝針(エダス)、投げ釣りに使われるテーパーライン(ある一定の長さの中で、徐々に太さが太くなっていく糸)や、砂ずりと呼ばれる撚り糸などもあります。
魚に直接影響を与えないものも含まれていますが、求められる性能と役割はハリス(リーダー)のそれに近いものがあります。
道糸にしろ、ハリスにしろ、求められる性能を十分に発揮するためには、それに相応しい特性を持つ糸が必要で、その根本となるのが釣り糸の素材の違いということになります。
逆に言うと、どのような釣りにおいても、釣果を伸ばすための方策の一つとして、道糸・ハリスそれぞれ状況に見合った素材の釣り糸を選択する必要があるということです。
それでは、次に2点目の釣り糸の素材の種類について詳しく見ていきたいと思います。
釣り糸の素材の種類による特徴と特性
すでに書きましたが、釣り糸の素材としては、ナイロン、フロロカーボン、ポリエチレン、そしてポリエステルが主流となっています。
ハイブリットラインといって、それぞれの特性の良い所取りをした複合ラインもありますが、ここでは各々の素材の基本的な特徴と特性を紹介するので、組み合わせ次第で特徴が変わる複合ラインの紹介は割愛します。
釣り糸は、使い易さを第一に考えれば、使い方によって概ねどの素材が適切なのか決まっています。
適切な素材の種類
- 道糸(ライン) ナイロン、PE(ポリエチレン)
- ハリス(リーダー) フロロカーボン
- 幹糸(モトス)、エダス PL(ポリエステル)
実際には、道糸とハリスで同じ素材のものを使うこともでき、例えばフロロカーボンなどは道糸としても使用され、モトスやエダスなどにも採用されています。
近年では、ポリエステルの道糸なども販売されるようになっており、一概に区分けしてしまうのは適切とは言えませんが、素材の特性から考えた場合に、最も適した使い方といえば上記のようになります。
それでは、各々の素材の特徴と特性について、触れていきたいと思います。
ナイロンラインの特徴と特性
ナイロン樹脂を使用した釣り糸は、比重は基本的に1以上であり、ゆるやかに水に沈みます。
しなやかさを持つラインとして、リールのスプールに馴染みやすく、糸の出もスムーズなので、特にエサ釣りにおいては万能の道糸として、圧倒的なシェアを占めています。
同じ太さの釣り糸を比較した場合、フロロカーボンラインより強度は高く、価格が安いというのが特徴です。
デメリットとしては、吸水性が高いことと、紫外線に弱いこと、糸グセが付きやすいことなどから、劣化スピードは決して遅くありません。
また、同じ道糸として使われるPEラインなどに比べると太いため、遠投が求められる釣りにおいては、使い勝手が悪い場合もあります。
道糸として使う場合のおすすめラインはコチラ
東レ(TORAY) ナイロンライン 銀鱗 スーパーストロングNEO 150m 2.5号 ゴールド
なお、ナイロンラインは伸びがあるラインなので魚の食い込みが良いという点から、ハリスやリーダーとして使用されることもあります。
ただし、その反面アタリは伝わりにくいというデメリットを合わせ持つことも覚えておきましょう。
ハリスとして使う場合のおすすめラインはコチラ
ユニチカ(UNITIKA) ハリス グンター ナイロン 50m 0.8号
PEラインの特徴と特性
PEラインは、高密度ボリエチレン素材の極細糸から作られた撚り糸で、4本撚りと8本撚りが一般的です。
比重は1未満で水に浮きますが、PEラインもナイロンラインと同様に道糸として使用される釣り糸です。
ナイロンラインと比べて2倍以上の引っ張り強度を持ち、細糸による非常に高い遠投性能を持つのが最大の特長で、ルアーフィッシングでのメインラインという印象が強いですが、投げ釣りや船釣りなどのエサ釣りでも使用されます。
また、伸びない性質から、魚のアタリが明確に伝わるというメリットもあります。
10年ほど前までは非常に高価なラインでしたが、近年は製造技術の向上からコストも下がり、他のラインと同じ程度の価格で入手できるようになりました。
ただし、細糸ほど絡みやすい、コスレや瞬間的な衝撃に弱い、ラインの滑りやすさから結び方が難しいなどのデメリットもあります。
最近は編み込みだけではなく、特殊コーティングを施すことで適度なハリをもたせているPEラインが使われています。
滑り性能の向上から耐摩耗性に優れ、撥水力も向上しており、ガイドの滑りが良いことから、更なる飛距離の向上に繋がりました。
なお、一部の釣りではハリスとして用いるケースもありますが、マイナーで使い勝手が難しいので、ハリスとしての使用はお薦めしません。
ルアーフィッシングでおすすめのラインはコチラ
エックスブレイド(X-Braid) アップグレード X8 200m 1号 22lb グリーン
投げ釣りのおすすめラインはコチラ
DUEL(デュエル) HARDCORE PEライン 1号 HARDCORE X4 投げ 200m 25m×4色
フロロカーボンラインの特徴と特性
フロロカーボン製の釣り糸は、ハリス(リーダー)として主流の素材で、エサ釣りであれ、ルアーフィッシングであれ、決してなくてはならない釣り糸となっています。
比重は1.6以上あり、ラインの素材の中では最も重く、早く水に沈みます。
ナイロンラインよりも張りが強く、擦れにも強いという点は、特に根回りを攻める釣りにおいては必要不可欠の特長です。
伸びが少ないことで魚のアタリを捉えやすいというメリットがある反面、急激な衝撃には弱く、結び方を誤ると結節強度が極端に下がるといったデメリットもあります。
フロロカーボンラインは非常にラインナップが多く、各々の製品で結節強度、衝撃強度、耐摩耗性、そしてしなやかさのバランスが異なります。
自分の仕掛けに見合ったラインが見つかれば、使い勝手の良さだけでなく、釣果の向上も十分に期待できます。
ハリスとしての強度としなやかさを最高レベルで兼ね備えたおすすめのフロロカーボンはコチラ
クレハ(KUREHA) ハリス シーガー グランドマックスFX 60m 1.5号
フロロカーボンは、道糸としても使われることがありますが、この場合はハリス用と違ってソフトタイプを使用します。
風の抵抗を受ける投げ釣りや、道糸を沈めたい落とし込み釣り、あるいは軽いジグヘッドやルアーを使うライトゲームなどでよく使用されます。
また、フロロカーボンの特長である張りの強さから、道糸そのものが根ズレを起こしやすい岩礁の釣りや波止際の釣り、穴釣りなどの使用にも向いています。
エサ、ルアーを問わず使えるラインナップ豊富なおすすめのフロロカーボンはコチラ
シーガー(Seaguar) シーガー フロロマイスター300 12lb(3号) 300m クリア
ポリエステルラインの特徴と特性
ポリエステルラインは、比重はナイロンより少し大き目で、張りに関してはフロロカーボンより強目といった感じです。
糸クセがないことで絡みにくく、ポリエステルの復元性によって、糸の捻じれやもつれが生じても、引っ張れば解消できるというメリットがあります。
吸水性も低く劣化による損傷が少ない反面、強度に関しては他の素材のラインに比べて伸びがない分弱いというデメリットがあります。
ハリスというよりは、胴突き仕掛けなどの幹糸(モトス)やエダスで重宝される釣り糸です。
仕掛け用ハリスとしては、一択で以下のラインがおすすめです
近年ではアジングやメバリングなどのライトゲームにおいて、極細のエステルラインがよく使われるようになりました。
ジグ単のような軽い仕掛けのキャスティング時に発生する、PEラインでのトラブルにうんざりしている方には、エステルラインを使用してみることをお勧めします。
ライトゲームでおすすめのエステルラインはコチラ
サンライン(SUNLINE) エステルライン鯵の糸 240m 0.3号/1.5lb
釣り糸の素材のまとめ表
最後に、釣り糸の素材ごとの特徴と特性のうち、釣り糸を選ぶ時に役に立ちそうな情報を表に纏めておきます。
リンク画像でアップしておきますので、初心者の方は早見表として活用いただければ幸いです。
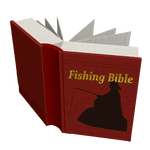
以上で、釣り糸の種類や素材に関して、是非とも身に付けておきたい基本知識の紹介を終わります。
この他にも、釣り糸を選ぶ時には、太さや強度、色、そして価格など、いくつかの要素が関わってきます。
特に強度(強力)については、釣り糸を選ぶ時に必ず必要となる『号数』に対するの知識が必要となってきます。
次回は引き続き、ライン選びの基本知識として、太さと強力について纏め、海釣りのメジャーな釣り方に対しては、具体的に適正な号数を紹介しようと思います。
【追記】
釣り糸の素材ごとの太さ(号数)と強度の関係と、種々多様な釣り方に適した釣り糸の種類と号数について、まとめて紹介している記事を作成しました。








