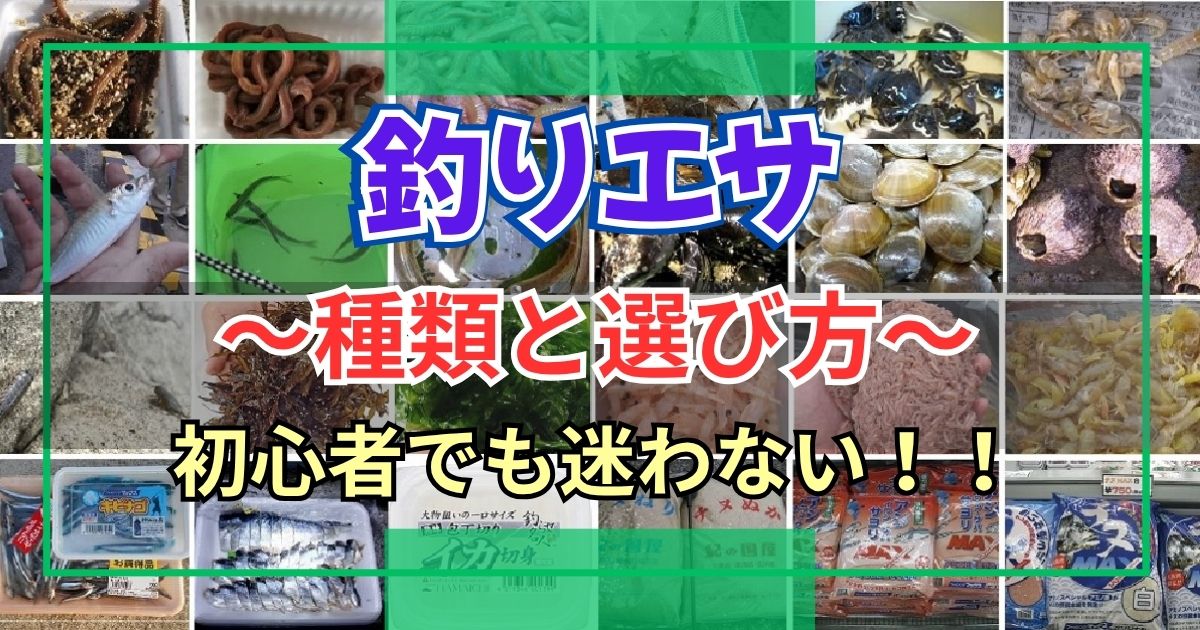どのような魚や釣り方に対しても、釣りエサは釣果に大きな影響を及ぼす要因の一つです。
理想を言えば、対象魚に合わせたエサの選択だけでなく、時期や時間、魚の活性、時にはその釣り場のベイトに合わせた使い方が出来れば一番です。
ただ、その域にまで到達しようと思えば、多くの知識や長年の経験が必要になり、それはもはやプロの域とも言えるでしょう。
現実的には、海釣りの中で最もポピュラーな堤防釣りにおいても、エサに拘る釣りをするのはごくごく一部の方だけだと言えます。
むしろ、大半の釣り人は、非常に多くの種類がある釣りエサの中から、幅広い魚種や釣り方に使える万能エサと呼ばれるエサを使用しています。
ここでは、これから釣りを始める入門者さんや、始めたばかりの初心者さん向けに、海釣りで使われるエサの種類と選び方を知ってもらおうと思います。
その上で、堤防釣り(波止釣り)では外せない、様々な魚や釣り方に対して汎用的に使える、おすすめの万能エサ3選について紹介します。
海釣りエサの種類と選び方 ~初心者におすすめの万能エサ3選~
それではまず、海釣りで使う釣り餌の種類を、いくつかに分類してみます。
エサは必ずしも釣具店や釣りエサ店で販売されているものだけではありませんが、あまり対象を拡げ過ぎると複雑になります。
ここでは、ごくごく一般的な釣りエサ店で取り扱っているものと、比較的簡単に現地調達ができるものを中心に取り上げます。
海釣りで使うエサの分類
海釣りに限ったことではありませんが、釣りエサは大きく分けると、以下の3つに分類されます。
- 生きエサ(活きエサ)
- 死にエサ(冷凍エサ)
- 人工エサ(配合エサ)
各々の特徴を簡単に示しておきましょう。
生きエサ(活きエサ)は食いの良さNo.1
生きエサは、エサの使用時に、文字通り生きている状態のエサを指し、エサの種類によっては活きエサとも表現します。
釣り針に刺したり、仕掛けに縛ったりして使いますが、エサ持ちの良さは、エサの大きさや生命力の違いにより様々です。
ゴカイやイソメなどと言われる虫類、カニやエビなどの甲殻類、アジやイワシなどの小魚(活き魚)などを中心に、アサリやカラス貝などの貝類や海苔などの植物も含め、まさに生きている状態で針に刺すエサです。
シラサエビやアサリのように撒き餌と付けエサを併用する場合もありますが、生きエサは釣り針に付けて使うものがほとんどですが、
エサによっては養殖ものもありますが、その点を除けば、エサに対して人の手が入らず、最も自然に近い状態のものであることから、食いの良さが特長のエサです。
死にエサ(冷凍エサ)は使いやすさ重視!
死にエサは、生物であっても、生きた状態を維持することが難しく、ほとんどが冷凍することで鮮度を保っているエサで、冷凍エサと呼ばれています。
鮮度が損なわれないように添加剤が使用されていたり、魚の食いの良さを向上させる加工が行われているものも多くあります。
海外からの輸入に頼ったものが多く、一部については、上記の生きエサを、冷凍した状態で使うものもあります。
死にエサは、生きエサに比べると魚の食いの良さという点では劣りますが、生きエサを釣り針に刺すのに抵抗がある人にとっては、非常に使い勝手の良いエサだと言えます。
また、生かし続ける必要がある生きエサに比べ、エサの保存という点においても、あまり気を使わずに済むというメリットがあります。
短期保存であれば、余ったエサを再冷凍して、次回の釣行に用いることも可能で、コストパフォーマンスの高さも期待できます。
人工エサ(配合エサ)は集魚に欠かせない
人工エサは、死にエサと同じく人が加工を施したエサですが、こちらは生物以外の化合物が使用されたものを差します。
人工エサは様々な材料を粉末化させ、これらを何種類も配合してできていることから、配合エサとも呼ばれます。
人工エサには、魚の嗅覚、味覚、視覚を刺激することで集魚効果があり、魚の食い気(活性)を高める役割を果たします。
海釣りでは、海水で練り合わせてダンゴにしたり、他の冷凍エサと混ぜてコマセ(撒きエサ)にするなど、集魚目的で使うことが多いのですが、一部は刺しエサ(練り餌)として使うこともあります。
配合餌はビニールパックなどに入っているものがほとんどで、必要な量だけ使えば残りは長期保管しておけるものがほとんどです。
海釣りで使うエサの種類と選び方
上記で挙げた生きエサ(活きエサ)、死にエサ(冷凍エサ)、人工エサ(配合餌)について、堤防釣り(波止釣り)でよく使われるものを中心に、それぞれのエサの種類とどのような魚を釣る時に選ぶのかを紹介します。
虫エサの種類と釣れる魚
虫エサ(主にイソメ、ゴカイ類)は生きエサの代表で、堤防釣りにおいては、どのような魚や釣り方に対しても使える、最もポピュラーな万能の釣りエサです。
ゴカイ類などで採取できるものもいますが、基本的には釣りエサ店で購入します。
- 青イソメ(青虫)
- 石ゴカイ(ジャリメ)
- マムシ(本虫)
- チロリ(スナメ)
- ユムシ
上記の他にも、袋虫やストロー虫、青コガネやタイムシといったものも、時期によっては大型の釣りエサ店で入手可能ですが、これらは一部の釣り人を除けば、ほとんど使う人はいないでしょう。

虫類の中では、アオイソメ(青虫)、イシゴカイ(ジャリメ)、そしてマムシ(本虫)の三種類が、大抵の釣りエサ店で購入できる人気の釣りエサで、釣り方や対象魚をを問わずに使える汎用性の高い虫エサになります。
虫エサは針持ちが良いので、堤防釣りの三大釣法を例に挙げると、ウキ釣りや探り釣りだけでなく、遠くまでキャスティングする必要がある投げ釣りでもメインのエサとして使われます。
更にその中で、生命力、針持ちの良さ、動き、匂い、コストなども含め、最も人気が高く流通量も多いのが青イソメです。
堤防釣りでは、青イソメはどのような魚に対しても使える最強のエサと言えるでしょう。
チロリはキスの特効エサとして、ユムシはマダイやカレイなどの投げ釣りで使われることが多いエサです。
虫エサはどのような釣りにも汎用的に使えるエサで、釣れる魚を挙げれば切りがなく、波止釣りにおいて釣れない魚はほとんどいません。
ただし、エサの種類によって、それぞれ異なる特長を持つので、ターゲットや釣り方、そしてコストを考慮して使い分けるのが良いでしょう。
エビ類、カニ類のエサと釣れる魚
虫エサの次に良く使われる生きエサはエビやカニなどの甲殻類ですが、これらも自然の環境に多く生息するエサであることから、魚の食いが良いエサです。
地域次第で自分で捕獲できるエサもいますが、採取するのも大変なので、釣りエサ店で購入する方がリーズナブルです。
- シラサエビ(スジエビ)
- ブツエビ(ヌマエビ)
- ボケ(スナモグリ)
- クモガニ(コメツキガニ)
- 岩ガニ
最も良く使われるエビはシラサエビやブツエビといった淡水エビ(活きエビ)と、海の磯場の砂地などに生息するボケで、堤防釣り(波止釣り)では比較的広範囲な釣り方で使用されます。

特に活きエビは比較的獲物を選ばずに使えるエサで、穴釣りや際釣りなどの探り釣りで、ロックフィッシュとの相性が抜群に良いエサです。
また、エビ撒き釣りといって、撒き餌と刺し餌の両方で使うことで、スズキ(ハネ)やクロダイ(チヌ)、メバルやアコウなど魅力的な魚を狙えます。
ボケはクロダイ(チヌ)の特効エサで紀州釣りや筏釣りなどのダンゴ釣りで良く使いすが、ブッコミ釣りでスズキやマダイ、カレイなどの大物を狙う場合にも使用されます。
また、カニについてはクモガニや岩ガニなどの小ガニを使いますが、コチラはヘチ釣り(落とし込み釣り)や前打ちなどでクロダイをターゲットにするのに使われることが多く、あまり汎用的に使えるエサとは言えません。
甲殻類は元気に生かしておくのに少々手間が掛かり、またコストも決して安くはありませんが、非常に食いの良いエサなので、大物狙いを含めて釣果は期待できます。
エサに使う小魚と釣れる魚
そして、フィッシュイーターを狙った活きエサといえば、やはり小魚になります。
- 小アジ(豆アジ)
- イワシ
- 銀平(ウグイ)
- ウリボウ(シマイサギの幼魚)
- オセン(スズメダイ)
- ドジョウ
小魚の多くは、現地の釣り場で調達できるというメリットがあり、豆アジやイワシが良く使われ、実績の高いエサになります。
銀平やドジョウは釣りエサ店で購入し、アジも釣るのが難しい時期なら、釣りエサ店で購入するのも良いでしょう。

活きエビと同じように、活かしておくのにブクブクが必要で手間が掛かりますが、呑ませ釣り(泳がせ釣り)やアオリイカのヤエン釣りでは必須です。
スズキやハマチ、サゴシ、シオ(カンパチの幼魚)、そしてヒラメなどのフィッシュイーターから、時にはアコウなどの高級魚まで堤防釣りであっても大物や高級魚が狙えるエサです。
アジやイワシが確保できない場合に、対象魚がスズキであれば、ウリボウやスズメダイを泳がせて使うこともあります。
また、対象魚によっては、ドジョウや銀平(ウグイ)、メダカなどの淡水魚を使うこともあります。
特にタチウオの引き釣りでは、ドジョウの食いが良く、これは死んでしまっても問題なく使えるのと、エサ持ちの良さで重宝されます。
貝エサの種類と釣れる魚
貝類はあまり汎用性の高いエサとは言えませんが、一部の対象魚にとっては食いの良いエサになります。
ほとんどは釣りエサ店やスーパーで入手可能ですが、一部は自分で採取する必要があります。
- カラス貝(イ貝)
- アケミ貝
- アサリ
- サルボ貝
- フジツボ
- カメノテ

貝エサが良く使われる対象魚にクロダイ(チヌ)がいますが、最も良く使われるのがカラス貝(イガイ)で、波止際の落とし込み釣り(ヘチ釣り)に使います。
カラス貝(イ貝)は釣りエサ店にも売っていますが、波止際に付着しているものをイガイ取り器を使って現地調達することも可能です。
アケミ貝もまたクロダイが中心(こちらは波止釣りではなく筏釣りやカセ釣りなどでの使用)のエサですが、カワハギやウナギを釣る時にも使われます。
アサリはカワハギの特効エサで、船釣りがメインの使用ですが、ある程度サイズが大きくなってくる晩秋以降であれば、堤防釣りの胴突き仕掛けでも使うことが出来ます。
サルボ貝はかなりマイナーで、大型の釣りエサ店でもほとんど取り扱っていませんが、堤防釣りのモンスターと言われるカンダイ(コブダイ)釣りに使われる特効エサです。
その他、フジツボやカメノテはテトラポッドや地磯などに付いているものを、比較的簡単に採取可能(ただし、このあたりの採取は漁業権が設定されていないか注意が必要)で、あまり知られていませんがカサゴに代表されるロックフィッシュの食いは抜群で、カワハギの狙い打ちなどでもエサ持ち良く使えます。
その他の生きエサと釣れる魚
その他、あまり使う人はいませんが、ベテランさんが使うようなエサの紹介です。
- フナムシ
- 海苔(アオサ)
- ホンダワラ

どこの堤防でも見かけるフナムシは、見た目はゴキブリのような感じなので、生理的に嫌悪される方も多いと思いますが、意外と様々な魚に対して使えるエサです。
現地調達が可能で、比較的エサ取りにも強く、ウキ釣りで狙うチヌやグレなどの上物を中心に、探り釣りのカサゴやメバルなどのロックフィッシュにも効果の高いエサです。
海苔(アオサ)とホンダワラは海洋性の植物ですが、前者はグレ釣りに使い、後者はブダイ釣りに使ったりします。
さて、ここからは死にエサ(冷凍エサ)の種類と対象魚について確認していきましょう。
死にエサ(冷凍エサ)の種類と対象魚
冷凍エサの種類の中で、最もメジャーかつポピュラーなエサは、エビ系のエサになりますが、いずれも釣りエサ店で購入して使用します。
- オキアミ
- アミエビ
- ボケ(スナモグリ)

冷凍エサといえば、真っ先にあがるのがオキアミで、刺しエサとしてだけではなく撒きエサ(コマセ)にも使用される、堤防釣りの万能エサです。
生エサタイプとボイルタイプがあり、エサの大きさも3種類~5種類、添加物に工夫を加えたものなど、各メーカーとも非常に多種多様な製品ラインナップを揃えています。
ウキ釣りや探り釣りで幅広い対象魚に使用できる反面、エサ持ちは良くないため投げ釣りでの使用は難しく、またエサ取りに弱いという側面も持ちます。
そして、こちらも堤防釣りでは必須のエサともいえるのがアミエビです。
通常のアミエビは粒が小さく、撒きエサとして集魚のために使われるのが一般的で、ファミリーフィッシングに代表されるサビキ釣りに欠かせない釣りエサです。
ただし、アミエビの中でも、サイズの大きなものだけを選別したものはサシアミ(大粒アミエビ)と言い、刺し餌として別途販売されています。
サシアミはアジやサヨリなどの青魚狙い限定のエサで、食いの良さはNo.1ですが、エサ取りに弱く針持ちが悪いという欠点があります。
もう一点、冷凍ボケは生き餌で紹介したものと同じで、死んでしまったものを冷凍パックにして販売されています。
ボケは死んでもあまり食いが悪くならないエサなので、行き付けの釣りエサ店で取り扱っていれば、コストメリットを考えるとコチラを使用するのも良いでしょう。
魚介系の冷凍エサの種類と釣れる魚
冷凍エサの中で、エビ系の次にポピュラーなのが魚介系の冷凍エサです。
魚介系の冷凍エサは釣りエサ店で購入できますが、その多くはスーパーなどで入手可能です。
- キビナゴ
- サンマの切り身
- サバの切り身
- イカの切り身
- アサリのむき身

キビナゴやイカナゴなどの小魚、サンマの切り身、イカの切り身ともにタチウオやカサゴを中心としたロックフィッシュのエサとして使用されます。
この中で意外と知られていないのが、イカの切り身の万能性で、チヌ、アナゴ、キス、小さく切って針付けすれば、アジやサバ、サヨリなどの青魚系にも使えます。
アサリのむき身は、生きエサのところでも紹介しましたが、やはり対象魚はカワハギになります。
魚介系の冷凍エサは、初心者が使う機会が少ないエサですが、それは釣り方の大半が初心者向きではないからです。
ただし、初心者でも取り組みやすい穴釣りや際釣りなら、エサ持ちも良く効果的に使えるので、一度試してみても面白いでしょう。
なお前述のように、サンマやサバ、キビナゴやイカの切り身、アサリのむき身などは普通にスーパーなどでも入手可能です。
スーパーで生の状態で購入してきて切り身に捌き、釣り場に持ち込んだほうが、釣りエサ店で買うよりも安くつくのでお得です。
上の写真に載っている左のキビナゴ(下段)や、中央のサバとサンマの切り身(上がサバ、下はサンマ)は、まさに管理人が釣行前にスーパーで買って用意したものです。
釣りエサ店で購入すると高いので、面倒でなければスーパーやコンビニで用意した方がコストメリットは高いです。
その他の冷凍エサと釣れる魚
その他にも様々な種類の冷凍エサがありますが、いくつかだけ紹介しておきます。
- 練りエサ
- サナギ
- 豚の脂身
- 鶏皮

練りエサは次項で紹介する配合餌にも部類するものですが、刺し餌として販売されているものは冷凍製品なので、コチラで紹介しておきます。
練りエサは集魚と食わせの両面の特性を持つエサで、もともと海上釣り堀で使用されることが多かったのですが、近年では波止釣りでも普通に使用されるようになりました。
特にチヌやアイゴ、カワハギなどに有効ですが、その他にも、実際に使ってみるとチャリコやベラなどのエサ取りも含めて意外と多くの魚種が釣れます。
冷凍サナギはほぼチヌに特化した釣りエサですが、匂いが強烈でこれを粉末にしたものが、次項の配合餌の集魚剤としてよく使われています。
変り種として一つ、豚の脂身や鶏皮を入れてみましたが、タコを釣る時にエギに縛り付けて使用します。
先ほどと同じように、豚の脂身や鶏皮はスーパーで用意するとタダのような安いエサですが、釣りエサ店で購入するとそこそこ高くつくので注意してください。
されでは、最後に人工エサ(配合エサ)の種類についても紹介します。
人工エサ(配合エサ)の種類

配合エサも非常に多くの種類がありますが、これについては特に分類は必要ないと思います。
配合エサの使い方のメインはとしては、撒き餌(コマセ)に混合して使用したり、ダンゴにしてポイントへ投入します。
配合餌の効果は集魚第一ですが、比重の違いによる沈降速度のコントロールや、濁りによる警戒心の緩和効果などもあります。
また、刺し餌として使う配合エサが、前項で紹介した『練り餌』になります。
練りエサは自分で使う針の大きさに合わせて練り上げるものと、始めから粒状になったものが販売されています。
意外と幅広いターゲット相手に使える練りエサですが、海中に入れると時間の経過とともに溶けるのでエサ持ちが悪く、投げ釣りなどの強いキャスティングが伴う、あるいは魚が食いつくまで長時間待つような釣りには向かないというデメリットもあります。
上記の紹介では、かなりマイナーなエサも含まれてしまいましたが、実は変り種のエサも含めると、まだまだ紹介できる釣りエサはたくさんあります。
海釣り経験が豊富な方の中には、自分独自で用意したエサを使用されている方もおり、そう考えるとエサの種類は無数にあるとも言えます。
本記事は初心者さん向けとして紹介していますが、エサの種類を知っておくことは、これから先、釣りの幅が拡がってきた時に有用な知識になるので、頭の片隅にでも留めておいてもらうと良いと思います。
初心者さんにおすすめの釣りエサ3選と使い方

それでは最後に、これから海釣りを始めようとしている入門者さんや、釣りを始めたばかりの初心者さんにお勧めの、堤防釣りで万能に使えるエサを3点だけ紹介しようと思います。
釣りエサを用意するのもお金が掛かるので、無駄に使わない・使えないエサを購入して、納竿時にマキエして捨てることになるのは非効率です。
もし、何を購入すれば良いのかが分からないという方には、以下の3点の中から釣りの種類に合わせて必要なものを購入してもらえば良いと思います。
右も左も分からなければ、生きエサコーナーで『アオイソメ 500円』
初心者の頃は、同行者がいなければ誰だって、右も左も分からない状態です。
インターネットで調べ物をして、最低限の釣具を用意し、『さあ、いざ釣行へ!』
釣りエサ店に寄ってみますが、実際にはエサをどのように購入したら良いのか・・・不安ですね。
アオイソメ(青イソメ)は生きエサコーナーで量り売りしているので、まずは生きエサコーナーを探してみましょう。
相場は地方によって違いますが、50gで500円程度が多く、500円単位で販売されているケースが一般的です。
都市近郊であれば300円もラインナップされていたりしますが、逆に地方へ行くほど相場は上がり高価になります。
人気のエサなので、すでにパックに入れられてカウンターに置かれている場合もありますが、置かれていなければカウンターの向こう側にいる店員に、『アオイソメ500円』と言って下さい。
使う時期やエサ取りの活性、もちろん釣り方にもよりますが、一人での釣行なら500円で半日から一日は釣りを楽しめるでしょう。

アオイソメは、魚の食いと針持ちが良く、どのような釣りにも使える万能エサなので、まだまだ自分の釣りが確立していない初心者さんには最もお勧めできるエサです。
おが屑や保湿された砂と一緒にパッキングされていますがその都度使う分だけ取り出して、残りはパックのままクーラーボックスの中にしまっておけば終日生きています。
残ったものを持ち帰って保存することも出来ますが、長期間は生きていませんので、次の釣行までに日が空くなら余った分はマキエして帰りましょう。
初心者に限らず中級以降になっても人気の釣りエサなので、これから先のあなたのフィッシングライフで、ずっとお世話になるかもしれません。
堤防釣りで使うアオイソメは、一部の大型のフィッシュイーターを除けば、釣り方や使い方を問わず、波止釣りの三大釣法(ウキ釣り、探り釣り、投げ釣り)すべてに使える釣りエサです。
波止釣りの三大釣法をご存じなければ、コチラをご参考にどうぞ!
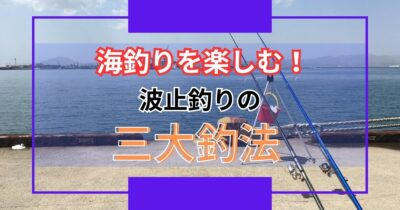
アオイソメが使えない釣り方はほとんどありませんが、アオイソメの特性を活かしたおすすめの使い方は、コマセを必要としない投げ釣り、ブッコミ釣り、チョイ投げ、穴釣り、際釣り、夜釣りのウキ釣りです。
生きエサは無理という方には【オキアミ】
女性アングラーを中心として、生きエサを針に付けるのに抵抗のある人は少なくありません。
それが虫エサであるなら、なおのことでしょう。
そんな人にお勧めなのが、青イソメと同じように、海釣りでは万能エサの一つとして扱われるオキアミです。

ただし、エサが柔らかいので魚の食いが良い反面、針持ちが悪く、どのような釣りにも使えるというわけではありません。
一般的なウキ釣りや、波止際やテトラポッドでの探り釣りには使えますが、強いキャスティングを必要とする投げ釣りなどには向きません。
また、オキアミは刺しエサ用がワンパックで400円~600円程度ですが、撒き餌用のブロックなら3kgでも1,000円程度と安価であることもあり、コマセ(撒きエサ)としても使われ、チヌやグレといった上物のフカセ釣りや、アジやマダイのカゴ釣りなど、刺しエサと同調させる釣りでは必須エサです。
先に紹介したようにオキアミには生タイプとボイルタイプがあり、サイズも複数種類ありますが、初心者が一般的な波止釣り使うのであれば、生タイプのMサイズのオキアミがお勧めです。
添加材などを使い、魚の食いを良くする工夫が施された製品も多いので、色々と試してみるのも良いでしょう。
余ったエサは持ち帰って冷凍庫で保管できますが、一度解凍したオキアミを再度冷凍すると、水分量が変わり身がグズグズになります。
アジやサバなどシーズン中の青魚に対しては問題ありませんが、フカセ釣りなど撒き餌との同調が必要な釣での再利用はおすすめは出来ません。
集魚力No.1 取りあえず用意しておきたい【アミエビ】
最後はファミリーフィッシングの代名詞、大人気のサビキ釣りに使うエサのアミエビです。
アミエビもオキアミと同じように基本は冷凍エサ(冷凍ブロック)ですが、溶かして冷蔵パックで販売されているものもあります。
また、管理人もよく使用しますが、近年は長期間常温保存できるタイプのアミエビも増え、ずいぶんと品質も向上してきました。

アミエビの最大の特長は、抜群の集魚力であり、基本的には撒き餌として魚を寄せるために使います。
堤防釣り経験の長い釣り人さんに、撒き餌の最強エサは何と聞けば、大半の方がアミエビと答えるでしょう。
アミエビはサビキ釣りのように単独で使うこともあれば、先に紹介したオキアミと混ぜ合わせたり、配合エサを練る時の材料の一つとしても使われます。
多くの釣り人にとっては、初夏から晩秋までの期間は、アジ・サバ・イワシなどの青魚がメインターゲットとなることから、サビキ釣りならアミエビのみで釣りに出掛けるのも珍しくありません。
また、初心者さんが五目釣りなどをする場合も、刺しエサだけでは釣果は安定しにくいので、アミエビをマキエしながら釣ると良いでしょう。
アミエビは冷凍ブロックであれば、八切り(1/8切り、約2kg)で500円~600円程度ですので、サビキ釣りの方はもちろん、それ以外の方もメインのエサと一緒に是非持っていって下さい。
ただし、アミエビはエサ取りと呼ばれる雑魚も寄せつけるので、エサ取りの多い夏場の撒き過ぎには注意が必要です。
海釣りエサについて良くある質問
最後に初心者さんを含め、海釣りで使うエサについて、よく寄せられる質問と回答を纏めておきましょう。
- 海釣りでどのエサを使えばよいか迷っています。初心者におすすめのエサは何ですか?
-
初心者さんには以下のような「汎用性の高いエサ」をおすすめします。
- 青イソメ・・・釣り方や魚種を問わず、幅広い釣りに使用できる。
- オキアミ・・・付けエサにも撒き餌にも利用でき、冷凍エサなので使いやすい。
- アミエビ・・・集魚効果抜群で撒き餌するだけで魚が集まります。
- 青イソメはどのように付ければいいですか?付け方にコツはありますか?
-
青イソメはそのまま口から刺して胴を通す通し刺しが一般的ですが、対象魚が口の小さいものなら頭を切って胴体部分を使ったり、長すぎる場合は胴体をハサミで切って使います。
青イソメの付け方には、通し刺し、縫い刺し、チョン掛け、房掛けなどがあり、どれも場面に応じて使い分けることが重要です。
青イソメの付け方やコツについて、詳細に紹介しているサイトがあるので、ご参考にどうぞ。
- オキアミはどのように付ければいいですか?付け方にコツはありますか?
-
オキアミは尻尾の根元部分から刺して胴体を通すのが一般的ですが、逆に頭の方から刺す場合もあります。
また、エサが自然に潮に乗って海中を落下するために尻尾の羽の部分をカットしたり、2匹を抱き合わせて針に刺す方法などもあります。
オキアミの付け方やコツについて、詳細に紹介しているサイトがあるので、ご参考にどうぞ。
- 余ったエサは持って帰れますか?どれぐらい保存できますか?
-
余ったエサを持ち帰れるかどうかはエサの種類によりますが、基本的には持ち帰らない方が良いエサの方が多いので、釣行時間に合わせて必要な分だけ用意することをおすすめします。
具体的に、生きエサ(青イソメなど)は鮮度が落ちやすく、冷蔵庫に入れて保存しておいても1週間も保たないので、持ち越すのはおすすめできません。
冷凍エサは、持ち帰って冷凍すれば期間は長く保存できるものもあり次回の釣行で使えるものがあります。しかしながら、大半は一旦解凍して再冷凍すると水分で身がふやけてエサ持ちが悪くなるため、これらについては持ち越しはおすすめはできません。
乾燥エサ・粉末系・人工エサなど保存性のあるタイプは、次回の釣行で使えることが多いので、持ち帰ると良いでしょう。
以上で、海釣りの中でも、特に堤防釣りでよく使う釣りエサ(刺し餌と撒きエサ)の種類の紹介と、釣りの入門者や初心者さん向けに、どのような釣りにでも使える最もポピュラーで汎用性の高いエサの紹介を終わります。
冒頭でもお話しましたが、釣りエサは魚や釣り方、その他様々な条件に応じて、適切なものが変わってきます。
色々な釣り方やシチュエーションを経験し、自分なりのエサの使い方を模索するのも面白いので、是非ともいろいろなエサを使ってみて下さい。
それでは、良きフィッシングライフを!!
近年では生きエサも含めてネット販売しています。
管理人自身は生きエサは弱らないのか?という懸念もあってネットで購入したことはありませんが、ユーザーレビューはそれなりに高い評価を得ているようです。
釣りエサ店が遠くにしかなかったり、入門者さんでまだ釣りエサ店へ買いに行くのに気が引ける方は、ネット購入を検討されるのも良いのではないでしょうか。
釣りエサ店で普通に売っていて、管理人が何度も使用したことのある、青イソメ、オキアミ(付けエサ用)、オキアミ(マキエ用)、アミエビについて紹介しておきます。